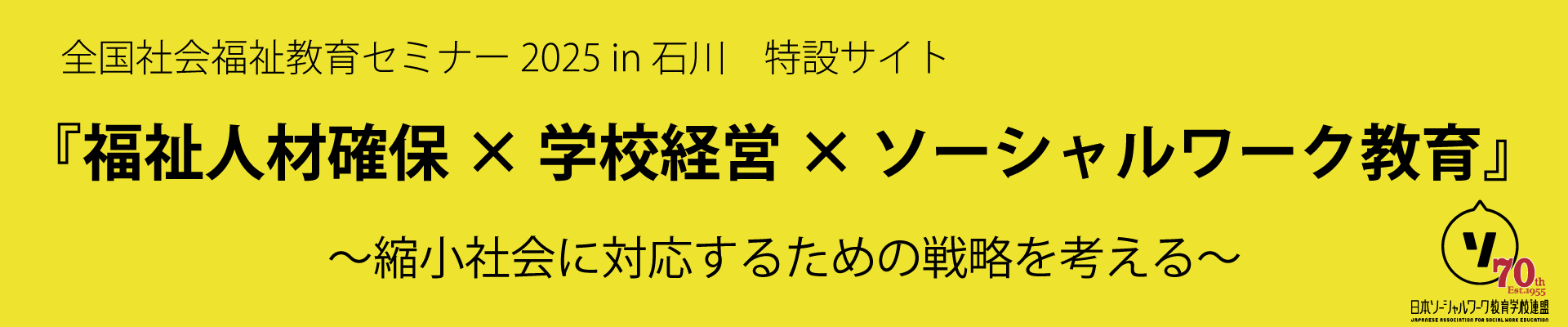DAY 1 (2025/12/13 sat)
10:30-10:50 【オープニング】
<登壇者>
中村 和彦(本連盟常務理事・北星学園大学)
堀岡 満喜子 氏(学校法人北陸学院 理事長・学院長)
10:50-11:50 【報告1】 『本連盟会員校の学生進路意向調査結果の要点』
本連盟では2019年度から毎年、社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の受験予定学生を対象に、全国統一模擬試験の受験者(毎年約8,000名規模)に対する調査を実施しています。そこでは、実習経験が就職意向や活動に与える影響、就職活動の状況、就職先の分野・設置主体、関心のある分野・課題など、福祉人材確保に資する基礎データを継続的に収集してきました。
本報告は、縮小社会における福祉人材確保の方策を検討するための基礎資料として、社会福祉士・精神保健福祉士国家試験合格を目指す学生の就職動向や意識の変化等について参加者と共有します。
<報告者>
伊藤 新一郎(本連盟常務理事・北星学園大学)
12:50-13:50 【基調講演】 『中央教育審議会答申「我が国の「知の総和」向上の未来像」の要点と今後の高等教育の課題』
2025年2月21日、中央教育審議会は「我が国の『知の総和』向上の未来像」と題する答申を公表し、人口減少社会における高等教育の持続性と競争力強化、グローバル人材育成、学修成果の可視化など、多面的な改革課題を提示しました。
とりわけ地方に所在する大学等にとって、定員割れや人材流出への対応は喫緊の課題であり、生き残りをかけて教育の質と持続可能性を高める取り組みが求められています。このような全国的動向は本連盟の会員校も例外ではなく、その行方は今後の福祉人材確保に直結するとともに、大学等の存続は地域の持続可能性の基盤でもあります。
本講演では、中央教育審議会委員がその要点を解説し、縮小社会における高等教育の展望と課題の要点について提示します。
<報告者>
森 朋子 氏(桐蔭横浜大学学長・中央教育審議会委員)
14:00-16:00 【鼎談】 『福祉人材確保×学校経営×高等教育×地方創生の未来を展望する~2040年を見据えて~』
今回の本セミナーのテーマの構成要素である「福祉人材確保」「学校経営」「高等教育」「地方創生」を横断的に取り上げ、【報告1】で示される学生の進路意向調査の実態や、【基調講演】で提示される今後の高等教育の方向性や課題を踏まえ、2040年を展望した福祉人材育成・確保の在り方を探ります。
また、ソーシャルワーク専門職養成教育の充実とソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士を目指す入学生の確保を両立させ、将来に向けた福祉人材の安定的確保を実現するための方策を展望する契機としながら、縮小社会における大学等と地域の関係やつながりの今後についても議論します。
<登壇者>
森 朋子 氏(桐蔭横浜大学学長・中央教育審議会委員)
坂井 元興 氏(内閣府地方創生推進事務局参事官)
中村 和彦(本連盟会長・北星学園大学)
<聞き手>
大原 裕介(本連盟理事・社会福祉法人ゆうゆう)
16:10-17:40 【セッション】 『福祉人材確保とソーシャルワーク実習の連動』
ソーシャルワーク専門職養成教育の成果が人材確保にも大きな影響を与えるが、なかでも実習教育は養成校外(ソーシャルワーク実践の現場)で行われ、養成校(教員)と実践現場(実習指導者)が協働して担う教育活動であると同時に、両者を接続するインターフェイス機能を有しています。
また【報告1】で示されるように、実習経験は学生の就職意欲や進路選択に大きな影響を与えていることから、今後の人材確保について考えるうえで実習教育の重要性を再確認することは意義があります。
本セッションでは、こうした実習の教育的意義と人材確保への効果を踏まえ、今後の実習の在り方や位置づけを登壇者それぞれの立場を踏まえ多角的に議論します。
<登壇者>
菊地 月香 氏(全国社会福祉法人経営者協議会研修委員長・社会福祉法人 同愛会 理事長)
渋谷 哲(本連盟相談役・淑徳大学)
仲井 達哉(本連盟理事・川崎医療福祉大学)
中條 大輔 氏(志學館大学)
<司会>
名城 健二(本連盟常務理事・沖縄大学)
DAY 2 (2025/12/14 sun)
10:00-11:30 【ワークショップ】『ソーシャルワーク教育のエデュケーショナルポリシー策定に向けて(中間報告)』
ソーシャルワーク専門職養成教育においては、プロフェッションとしてのソーシャルワーカー像を明確にし、その能力形成を体系的に支える枠組みが求められています。米国ではEducational Policy and Accreditation Standards(EPAS)に基づくコンピテンシー基盤型教育が定着しており、本連盟ではそれを含めた海外の動向を参照しつつ、2024年度から日本版エデュケーショナルポリシー(EP)策定に向けた検討を始めました。
実践現場では、日々の支援内容や業務が「ソーシャルワーク」として認識されにくいという課題も指摘されているなかで、羅針盤となるEP作成は教育と実践現場の接続や連携を強化していくうえで、また、昨今の高等教育における質保証の課題への一つの対応としても位置づけることができます。
本ワークショップでは、現場実践とコンピテンシーとの関係性を共有し、日本の風土や地域性を踏まえた日本版エデュケーショナルポリシーの意義と可能性を参加者同士の意見交換をベースに考えます。
<司 会>
渡辺 裕一 (本連盟理事・SWEP_PJ・武蔵野大学)
<説 明>
南野 奈津子 氏(SWEP_PJ・東洋大学)
11:30-12:30 【報告2】『令和6年の能登半島地震・豪雨災害における北陸学院大学学生の被災地支援状況』
2024年1月の能登半島地震・9月の豪雨災害において、北陸学院大学の学生は地域の要請に応え、災害ボランティアセンター運営支援や住宅片付け、被災者ニーズ調査など、多様な支援活動に参画しました。その後は全国の会員校に広がり、20大学以上が参加する「Disaster Welfare Assistance Student (DWAS)」ネットワークへと発展しています。
学生による被災地支援は、地域社会を支える力となるとともに、実践を通じた学びがソーシャルワーク専門職としての学びを通じた学生の成長や将来の就業意識にもよい影響を与えています。本報告では、北陸学院大学学生による災害支援活動の実際とその教育的意義を共有します。
<報告者>
北陸学院大学学生ほか
<モデレータ>
田中 純一 氏(北陸学院大学)
<ソ教連災害活動報告>
山本 克彦 氏(本連盟災害対応部会長・日本福祉大学)
13:30-15:00 【報告3】『ソーシャルワーク実習の充実に向けた令和7年度社会福祉推進事業(厚生労働省補助金事業)の経過報告』
令和3年度から開始された新カリキュラムにより、社会福祉士養成課程のソーシャルワーク実習は時間数が増加し、複数箇所での実施が義務づけられました。養成校の多様な形態や地域性のもとで、実習教育の水準をいかに確保するかは、ソーシャルワーク専門職養成教育と福祉人材確保に直結する重要課題です。
令和7年度の社会福祉推進事業では、養成校・学生・実習指導者を対象にした各種調査を通じて、新カリキュラムにおける実習教育の現況を把握し、その充実に向けた検討を進めています。
本報告では、これらの調査の速報を紹介するとともに事業の経過を報告します。
<報告者>
石附 敬 氏(事業委員・東北福祉大学)
増田 和高 氏(事業委員・武庫川女子大学)
<司会>
髙良 麻子(本連盟副会長・法政大学)
15:00-15:10 【クロージング】
<登壇者>
山野 則子(本連盟副会長・大阪公立大学)
DAY 3 (2025/12/15 mon) 【オプショナルツアー】
09:00-15:00(予定) 『ソ教連会員校の学生が支援活動している奥能登の被災地をバスでめぐり、歩く』
能登半島地震の被災地では、地元の北陸学院大学をはじめ全国各地から集まった学生が、DWASののもとで支援活動を展開し、地域を支える大きな力となりました。
近年、相次ぐ災害の中で、会員校は教育機関としてソーシャルワーク専門職を育成するだけでなく、建物や敷地、教員や学生といった多様な資源を備えた「地域の社会資源」としての役割も担っています。過去の災害でも学校が避難所や支援拠点となった例があり、学生や教職員が地域住民と共に歩んできました。ソーシャルワークを学ぶ学生にとって、被災者と向き合う経験は「福祉を学ぶ意味」を体感し、将来の専門職像を形づくる大きな学びとなっています。
本ツアーは、会員校の学生が支援活動している奥能登の被災地へ足を運び、その実際や学生による災害支援活動について知ることで、災害多発時代における教育と地域、人材育成と防災・復興をつなぐ意義を共に考える機会とします。
■ 日 時:12月15日(月)09:00~15:00(予定)
■ 定 員:20名(最少催行人数15名)
■ 参加費:6,600円
■ 金沢駅~輪島市門前町深見地区~門前町道下仮設住宅~金沢駅
■ ガイド:田中純一・山本克彦ほか